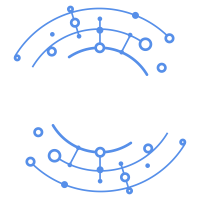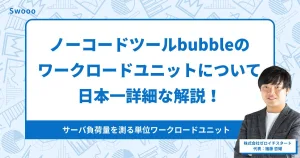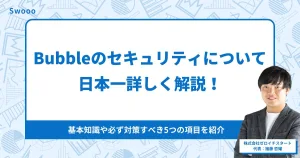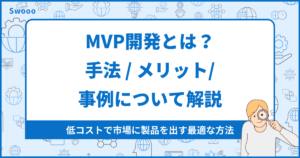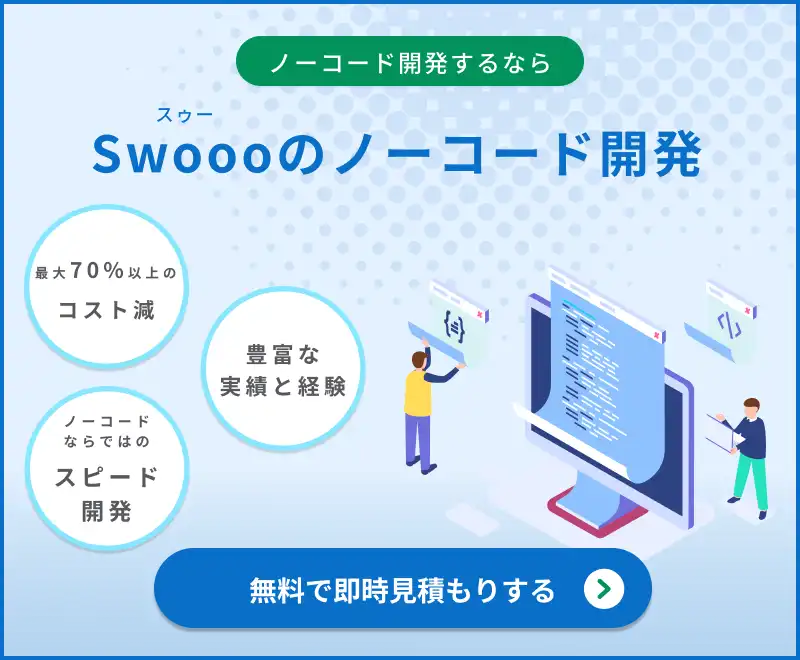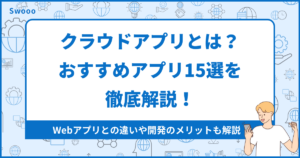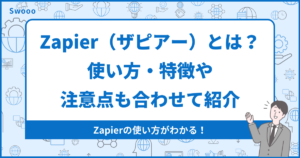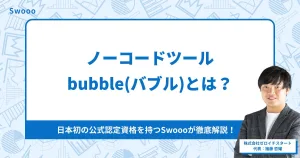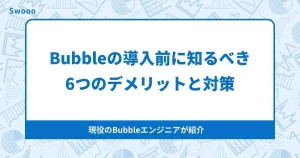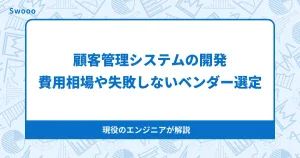Bubbleも決して万能ではない!導入前に知るべき6つのデメリットと対策
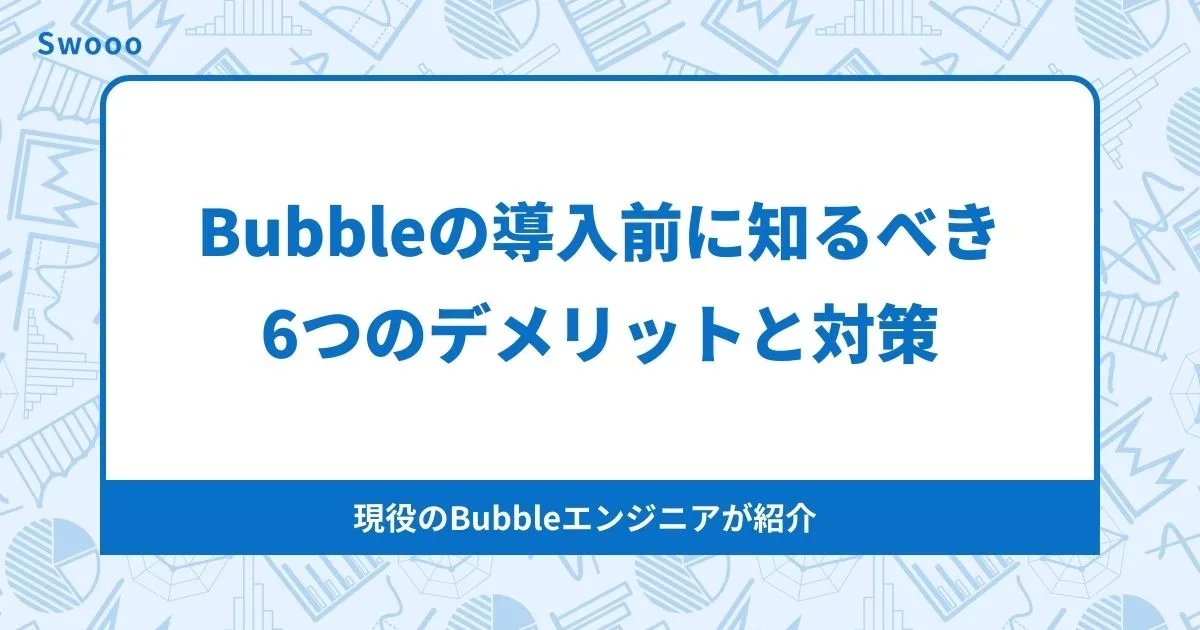
Bubbleはノーコードの中でも、最も高度なアプリ開発ができるツールの一つです。
開発コストと時間を大幅に削減できるため、スタートアップやMVP開発で高い効果を発揮します。
しかし、「Bubbleさえ使えばなんでもできる」という誤解は危険です。
インフラの制約、セキュリティの限界、コード表現の制限など、Bubbleには明確なデメリットが存在します。これらを理解せずに導入すると、開発の行き詰まりや後戻りできない構造的課題を抱えることになります。
本記事では、Bubbleの6つのデメリットと具体的な対策を、Bubble公認エージェンシーの視点から解説します。
当社Swoooは、国内初のBubble公式開発試験に合格したBubble開発会社です(※”国内初”は公表情報ベースであり、時点・定義により変わり得ます)。

技術力だけでなく、新規事業の文脈における包括的な支援も得意としております。
- 新規事業を立ち上げたいが、開発に大きな予算はかけられない
- 企画やデザインを含め、ワンストップで支援してくれる開発会社に頼みたい
- Bubbleのデメリットを踏まえた最適な技術選定をしてほしい
このような方はぜひ一度、当社Swoooにお問い合わせください。
この記事からわかること
Bubbleを導入する前に知っておくべきデメリットと、その対策がわかります。
・Bubbleの6つのデメリットと具体的な対策
・Bubble導入が向かないプロジェクトの特徴
・デメリットを踏まえた正しい活用方法
▼ ノーコードツールbubbleとは?こちらで徹底解説しています。
目次
Bubbleの6つのデメリットと対策
Bubbleには大きく分けて6つのデメリットがあります。
ただし、どのデメリットにも対策が存在します。正しく理解すれば、Bubbleは強力な開発ツールになります。
Bubbleのデメリット① インフラ環境の自由度や拡張性を欠く
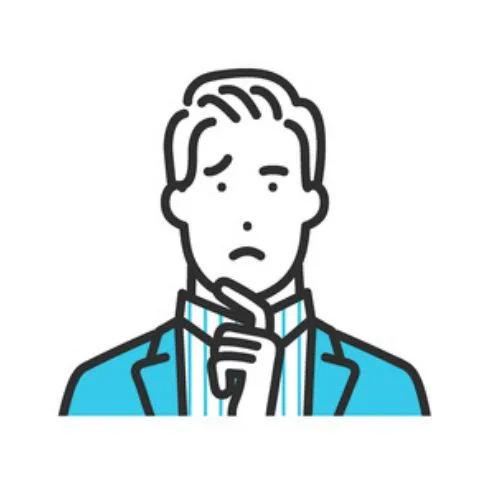
Bubbleって、AWSとか自由にサーバー選べないの?
Bubbleはインフラ管理をユーザーが行う必要がありません。これは開発の敷居を下げるメリットがある一方で、自由度や拡張性に限界があります。
Bubbleアプリは指定されたクラウド上でしか動作できない
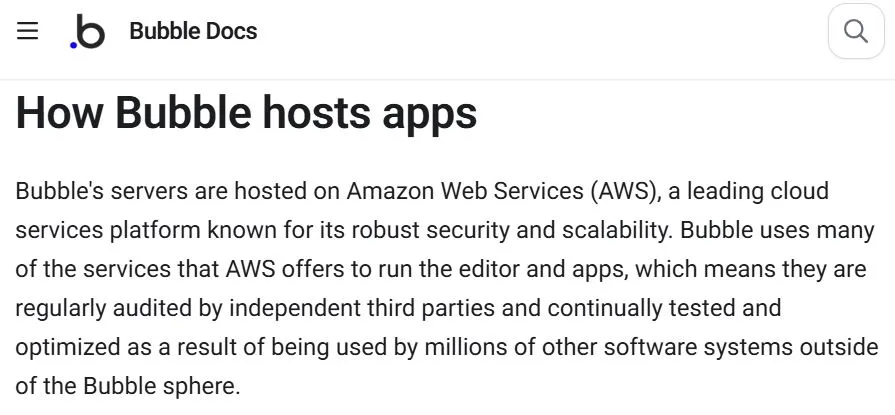
従来の開発では、AWSやAzure、GCPなど、クラウド基盤を自由に選べます。
しかしBubbleは、Bubble社が提供するクラウド環境でのみ稼働します。具体的には、BubbleはAWS上でホスティングされており、Dedicated instanceプランではホスティングリージョンを選択できる場合もあります(出典:How Bubble hosting works、Dedicated instance)。ただし、自前のインフラへ自由に移設できるわけではありません。
また、サービスの規模が拡大するにつれて、アーキテクチャ上の制約が顕在化しやすくなります。
高トラフィック時の安定性は設計とプラン次第
Bubbleは中小規模のトラフィックには十分対応できます。
高トラフィック時の安定性は「同時接続数」だけで決まらず、ページ設計・検索/DBクエリ・ワークフロー構成など”作り方”と、Workload(WU)・プラン設計に大きく左右されます。そのため、大規模化が見込まれる場合は、早い段階からWorkload/App Metricsで負荷を計測し、重い処理は外部API/外部DBに逃がすなどの分離設計を前提に検討しましょう(出典:Performance and scaling)。
対策:MVP開発としての利用や、外部APIとの連携
インフラの自由度が必要な場合や、大規模化が見込まれる場合は、Bubbleをフルスタック構築のみに頼らず、要件に応じて外部サービスと組み合わせることが重要です。
- BubbleをMVP開発に限定し、本格開発は別基盤へ移行する
- 外部APIや外部DBを活用し、Bubble側の負荷を最小限に抑える

Swoooでは、将来の規模拡大を見据えた設計をご提案しています。「最初からBubbleで全部作る」のではなく、フェーズに応じた最適な技術選定が重要です。
▼ MVP開発について解説しています。
Bubbleのデメリット② データの保持やセキュリティに限界がある

Bubbleでセキュリティが求められるサービスは作れる?
Bubbleは内部にデータベースを持っていますが、データ保持やセキュリティ面にいくつかの限界があります。
データベース構成の自由度が限られる
Bubbleは基本的に「1アプリ=Bubble内蔵DB(開発/本番環境で分離)」の前提で設計されており、RDBのように複数DBへ分割・分散(シャーディング/クラスタリング)して運用する自由度は高くありません。
大規模データや高負荷が見込まれる場合は、外部DB(例:PostgreSQL等)や外部バックエンドと連携し、Bubble側のDB負荷を抑える設計が現実的です(出典:Bubble公式マニュアル – Data tab)。
HIPAA準拠が必要なアプリはBubble公式として推奨されない
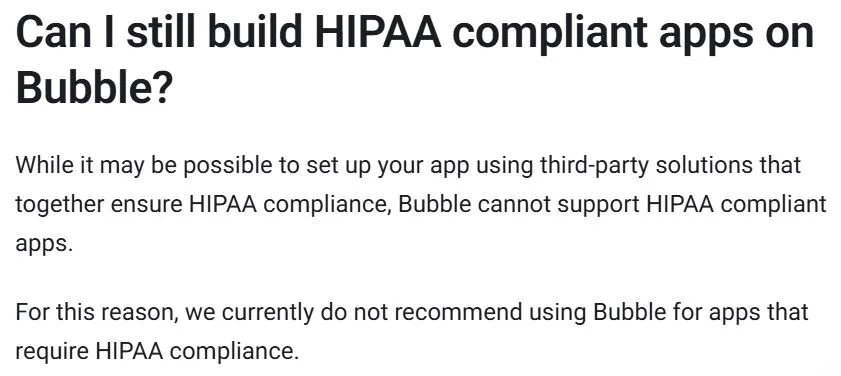
医療で求められるHIPAA準拠について、Bubble公式は「HIPAAコンプライアンスが必要なアプリの構築はサポートしていない」と明記しています(出典:Bubble公式 – HIPAA)。
第三者サービスとの組み合わせで対応できる可能性はありますが、これは”抜け道”ではなく、専門家の支援を得た上で慎重に判断すべき領域です。HIPAA準拠が必須のプロダクトでは、Bubble単体での開発は推奨されません。
対策:外部DBの使用や、フロントエンドのみのBubble活用
セキュリティ要件が高いプロジェクトでは、以下の対策が有効です。
- データベースはSupabaseやFirestoreなど外部サービスに配置する
- BubbleはUI/UX構築のみに使用する
- セキュリティが求められる処理はバックエンド側で担保する
▼Bubbleのセキュリティに関するさらに詳しい解説はこちら
Bubbleのデメリット③ 開発言語やコード描画手法の制約を受ける
BubbleはUI構築には優れていますが、使用できる言語に制約があります。
アプリ内部で任意のサーバーサイド言語を直接実行できない
Bubbleはノーコード基盤のため、アプリ内部で「任意のサーバーサイド言語(Python/Go等)を直接実行する」ことはできません。
複雑な計算・機械学習・バッチ処理などは、外部API(自前サーバー/クラウドFunctions等)として切り出し、Bubbleから呼び出す構成が一般的です(出典:Bubble公式マニュアル – The client-server model)。
SEO集客が主戦場のメディアでは運用難易度が上がる
Bubbleでもメタタグ設定やサイトマップ公開など、基本的なSEO設定は可能です。
一方で、ページ構成や動的コンテンツの出し方(クライアントサイド描画中心)によっては、インデックスや表示速度の最適化に”工夫”が必要になり、CMS特化ツールより運用難易度が上がるケースがあります。SEO集客が事業の主戦場になる場合は、WordPress等のCMSと役割分担(メディア=CMS/業務アプリ=Bubble)も含めて設計するのが現実的です(出典:Bubble公式マニュアル – SEO / metatags)。
対策:生成AIとのAPI連携や、WordPressとの併用
SEO要件が高い場合や、複雑な処理が必要な場合は以下の手法が有効です。
- SEO部分はWordPressで構築し、Bubbleは業務アプリのみ担当する
- 外部API経由でデータ連携する
- AI処理など負荷の高い処理は外部クラウドに任せる
▼Bubbleでできること/できないことの詳細はこちら
Bubbleのデメリット④ チーム開発には向いていない
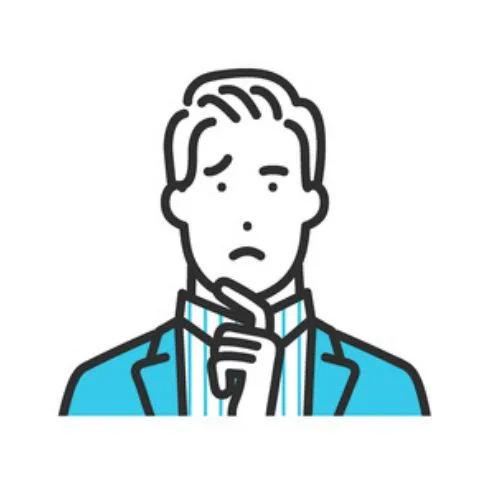
複数人で同時に開発できないの?
同時編集・マージ運用にはルール整備が必須
BubbleにはGit同等ではありませんが、バージョン管理(Version control)やブランチ機能が用意されています(出典:Bubble公式マニュアル – Version control)。
ただし、複数人での同時編集やマージ運用は、ツール特性上ハードルが上がります。上書きによるトラブルを防ぐため、役割分担やルール整備が必須です。
対策:上位プランの機能活用と運用ルールの策定
Bubbleの上位プランには「開発ブランチ」と「比較機能」があります。
これらの機能を活用し、担当領域の明確化・編集タイミングの調整など運用ルールを整備すれば、少人数チームでの連携開発は十分に可能です。
▼Bubbleの料金プランに関する詳細はこちら
Bubbleのデメリット⑤ ランニングコストの高騰に注意が必要
バージョン・開発者数・サーバー稼働量に応じて従量課金が発生する
Bubbleは月額固定のプラン料金に加えて、ワークロードユニット(WU)という従量課金制度があります。WUとはサーバー作業量の指標で、各プランに月次WUが含まれています。含まれるWUを超過した場合、追加料金(overage)が発生します(出典:Bubble公式 – Pricing and workload)。
サービスの利用者が増えたり、複雑な処理が増えたりすると、プランの引き上げや追加課金が必要になる場合があります。
の仕組み解説-jpg.webp)
対策:外部APIやDBの活用でBubble側の負荷を軽減
ランニングコストを抑えるには、以下の対策が有効です。
- BubbleをUI中心に使い、負荷の高い処理は別のクラウドに逃がす
- 外部APIやDBと接続した構造にすることで、料金を固定化しやすくなる
▼ワークロードユニットについての詳細はこちら
Bubbleのデメリット⑥ アプリやデータの移行性が損なわれる

将来、Bubbleから別のシステムに移行できる?
Bubbleでは開発物のソースコードをエクスポートできない
Bubbleで作ったアプリは、そのまま別の基盤に移すことができません。
将来的に「リプレイス(作り直し)」の必要が生じた場合、大きな障害となります。
DB構造や処理ロジックがBubble独自のため、他プラットフォームへの移行が困難
Bubbleはデータベース構造や処理ロジックを独自の方式で構築します。
そのため、アプリが成長するほど、他のプラットフォームへの移行が難しくなります。後戻りのコストが高くなる点には注意が必要です。
対策:事業のロードマップを作成し、移行タイミングを事前に設計する
移行リスクを最小限に抑えるには、最初から将来のロードマップを設計しておくことが重要です。
- MVP段階はBubbleで高速に開発する
- 成長フェーズでフルスクラッチへ移行する
- 移行時期を最初から計画に組み込んでおく

Swoooでは「Bubbleで作って終わり」ではなく、将来の移行を見据えた設計をご提案しています。事業の成長フェーズに合わせた技術選定が、長期的なコスト削減につながります。
▼ MVP開発について詳しく解説しています。
「自社プロジェクトにBubbleが適しているか判断できない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。