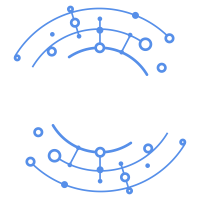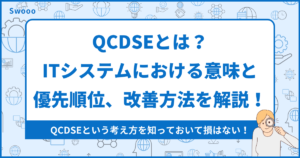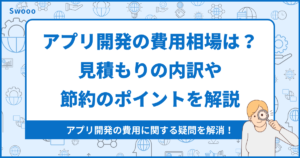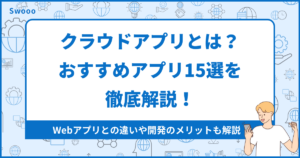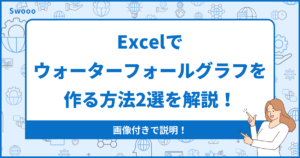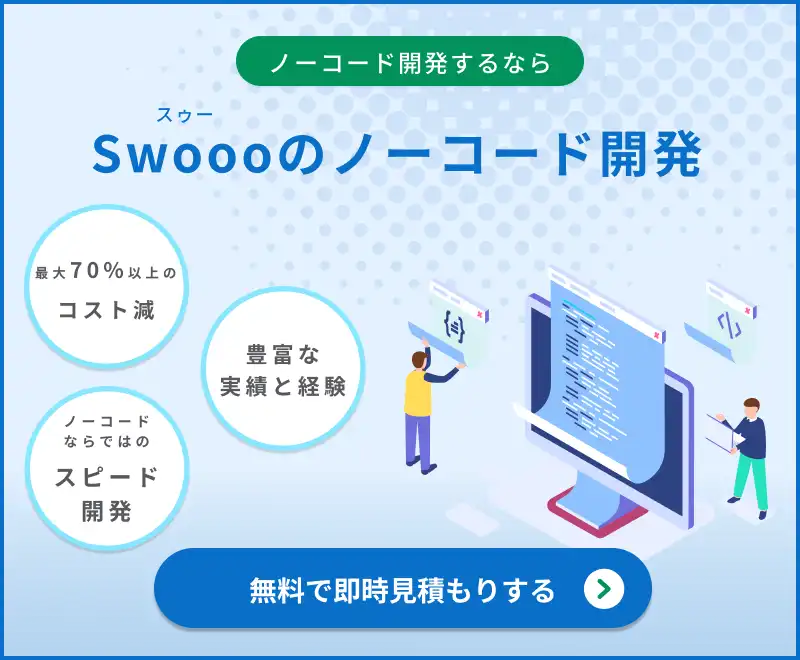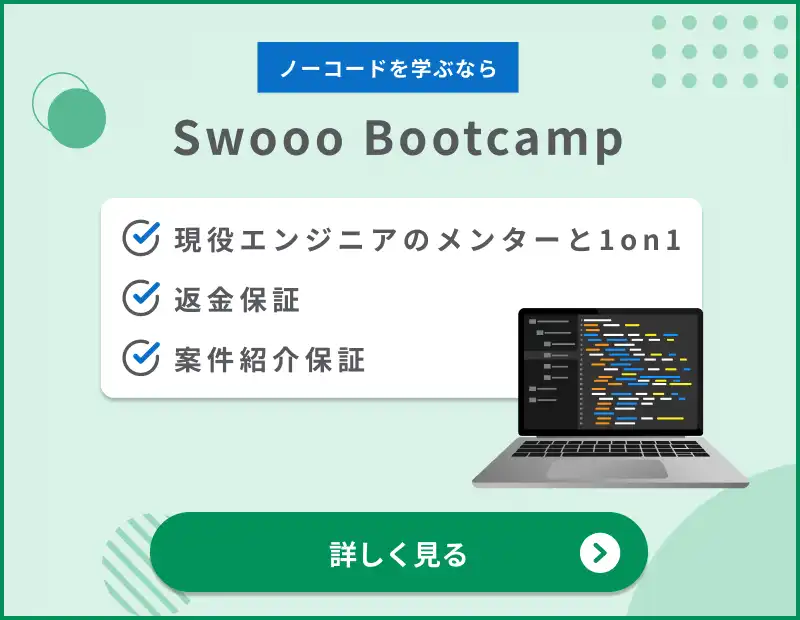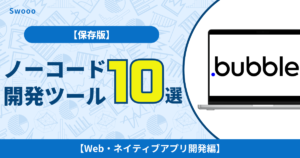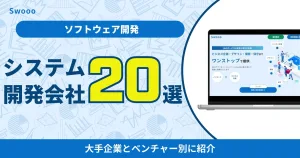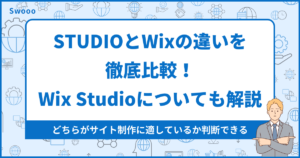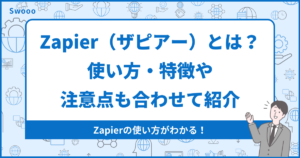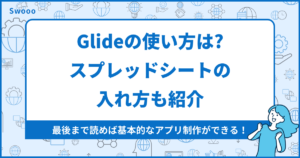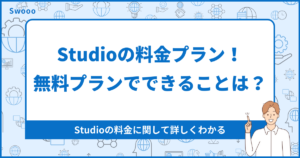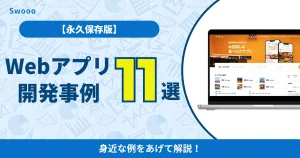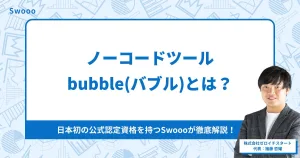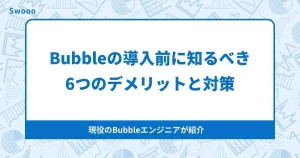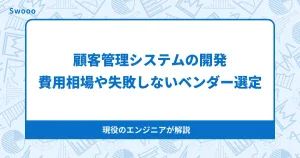【業務改善】QCDのフレームワークとは?|メリットや使い方を解説
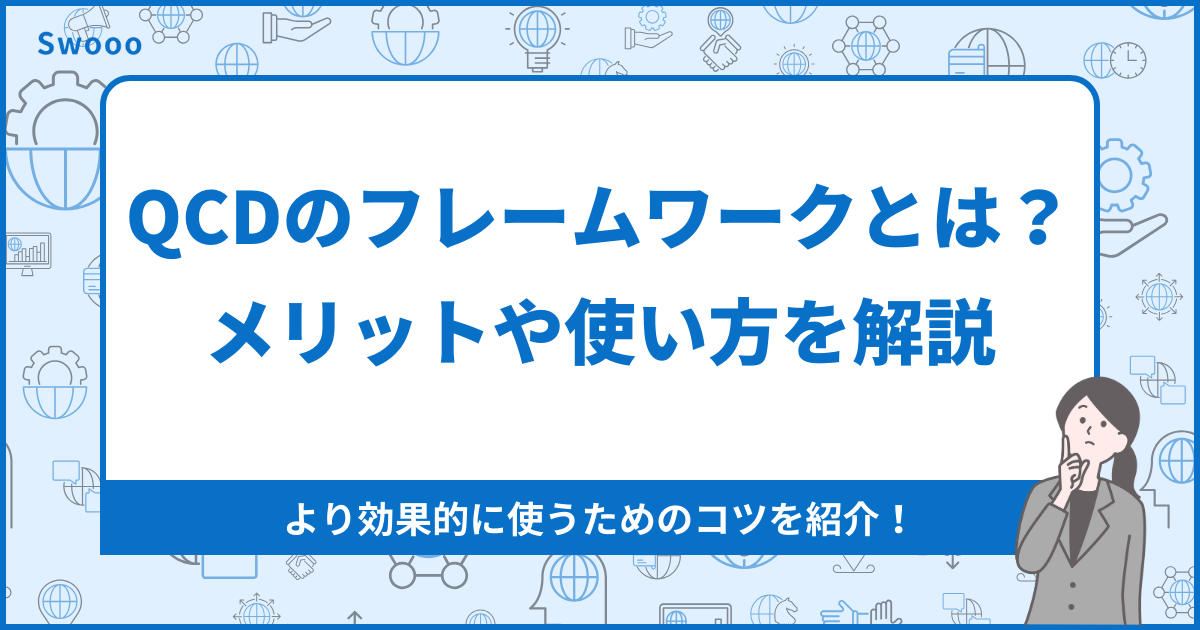
「納期を気にしすぎて品質が落ちてしまう」「どうしてもお客さまからの継続的な発注が受けられない」このような悩みを抱えていませんか?
そんなあなたにおすすめしたいのがQCDフレームワーク。
うまく利用することで、品質の向上やコスト削減につながるため、多くの注目を集めている考え方です。
今回は、QCDフレームワークとは何か、QCDフレームワークを使うメリットや使い方、より効果的に使うためのコツなども紹介します。
目次
QCDフレームワークとは?

そもそも、QCDとは以下の3つの単語の頭文字をとった言葉です。
- Q:Quality(品質)
- C:Cost(費用)
- D:Delivery(納期)
製造業の生産管理における業務改善に対して開発された、「品質」「費用」「納期」の3項目を重視する考え方をQCDフレームワークと言います。
以下では、3つの単語についてそれぞれ解説します。
Q:Quality|品質が最優先
1つ目は、Quality(品質)です。
QCDフレームワークでは、最初が「Q」であることからもわかる通り、「品質」が最も重要な要素だとされています。
万が一、品質が悪く不良品を大量に製造してしまった場合、命に関わる問題に発展する可能性が高いからです。
もちろん、費用や納期をおろそかにして良いわけではありません。費用が大きくなったり、納期が遅延すると、お客さまに甚大な被害を及ぼすかもしれません。
しかし、費用や納期による被害がなければ、品質を最重視しましょう。
C:Cost|初期段階の協議が重要
2つ目は、Cost(費用)です。
費用がかかる1番の原因は、追加や修正です。
そして、追加や修正が発生するのは、初期段階のコミュニケーション不足が原因だと考えられます。
お客さまとのコミュニケーションを通じて、製品が”お客さまに求められた品質”に達することが重要です。
このことからも、品質を最も重視する理由がお分かりいただけるのではないでしょうか。
D:Delivery|納期を絶対視しない
3つ目は、Delivery(納期)です。
納期はお客さまとの関係を維持する上で、とても大切な要素になります。
常に納期に遅れていたら、お客さまからの信頼が得られず、継続的な受注につながりません。そのため、基本的に納期は遵守することが大切です。
一方で、納期に間に合わせようとするあまり、品質が下がってしまうことも十分考えられます。納期に間に合わないことが分かった際、人員を補充しようとする場合があるでしょう。
しかし、プロジェクトをあまり理解していない人員が補充されると、かえってプロジェクトの進捗が遅くなることも考えられます。
「人員を補充しない方が良かった」となる可能性が高いので、納期に間に合わないからと言って、むやみに人員を補充するのは避けましょう。
QCDのフレームワークを活用するメリット4つ
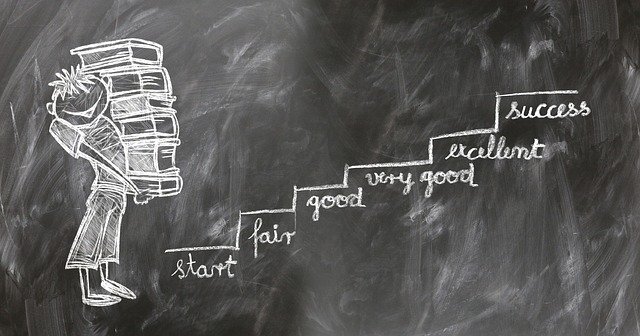
ここでは、QCDフレームワークを活用するメリットを4つ紹介します。
- 品質が向上する
- コスト削減できる
- 業務の無駄が省ける
- 労働環境が改善される
それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。
品質が向上する
1つ目は、品質が向上することです。
先ほども紹介した通り、QCDのフレームワークでは品質を最優先に考えます。
そのため、QCDフレームワークに則って製造すれば、品質が向上することは間違いありません。
品質が向上すればお客さまに喜んでもらい、今後の継続的な発注にもつながる可能性が大きくなるでしょう。
コスト削減できる
2つ目は、コスト削減できることです。
「品質を高くすると、コストが大きくなるのでは?」と考える方もいるでしょう。しかし、先ほども紹介したように、品質管理を徹底すると、追加や修正依頼を減らせます。
追加や修正には多額の費用がかかることが多いため、それだけでコストを削減できるでしょう。
また、品質を重視するといえ、過剰に高品質にする必要はなく、お客さまと協議をした上でクリアすべき品質になれば問題ありません。そのため、不必要なまでにコストをかけるのではなく、必要に応じてコストを削減できます。
業務の無駄が省ける
3つ目は、業務の無駄が省けることです。
QCDフレームワークは業務改善の一環のため、この考え方を導入すると、業務においての無駄が省けます。
業務にかける時間が減ることで、従業員の生産性が向上するでしょう。
労働環境が改善される
4つ目は、労働環境が改善されることです。
3つ目のメリットである「業務の無駄が省ける」ことで、1つの業務にかける時間が減り、残業を減らせるでしょう。
従業員の労働環境が改善されることで、日頃の働きぶりが良くなり、高品質な製品の製造も見込めます。
QCDフレームワークの使い方3つ

ここでは、QCDフレームワークの使い方を3つ紹介します。
- 優先順位をつける
- 組織課題を明確にし業務を改善する
- 部門を横断した共通の目標を立てる
それぞれの使い方について、以下で詳しく解説します。
優先順位をつける
1つ目は、優先順位をつけることです。
会社において業務を行うとき、大抵の場合は優先順位をつけることになるはずです。
その際にQCDフレームワークを使うことで、お客さまに適切な優先順位を決定できます。
優先順位が決まれば、お客さまに適切なサービスの提供ができるようになるため、成果を上げやすくなるでしょう。
優先順位の付け方について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
組織課題を明確にし業務を改善する
2つ目は、組織課題を明確にし業務を改善することです。
Q・C・Dのそれぞれにおいて、どのような課題があるのかを洗い出します。これにより、質・費用・納期というシンプルな3つに課題が分けられるので、意見が出しやすくなります。
意見が出やすいと、業務改善に向けた意見が多く出てくるため、素早く業務改善ができるようになるでしょう。
部門を横断した共通の目標を立てる
3つ目は、部門を横断した共通の目標を立てることです。
組織がいくつかの部門で分かれていることが多くありますが、サービスや商品によっては部門を横断して取り組むことが必要です。
それぞれの部門では異なる目標を持っているため、必ずしも同じ方向を向いていない可能性があります。
そこで、QCDフレームワークを用いることで、お互いの認識を擦り合わせやすくなるでしょう。
QCDフレームワークの効果を高めるコツ2つ

ここでは、QCDフレームワークの効果を高めるコツを2つ紹介します。
- 目標設定を明確にする
- 「PMBOK」「QC七つ道具」と一緒に使う
それぞれのコツについて、以下で詳しく紹介します。
目標設定を明確にする
1つ目は、目標設定を明確にすることです。
あたりまえですが、どの目標を達成するためにQCDフレームワークを用いるのかを決めておかないと、あまり効果は期待できません。
決めた目標に対しての優先事項を決めたり業務改善がなされたりするので、目標設定を明確にすることは非常に大切だといえるでしょう。
「PMBOK」「QC七つ道具」と一緒に使う
2つ目は、「PMBOK」「QC七つ道具」と一緒に使うことです。
あくまでQCDフレームワークはツールであり、目標を達成するためのプロセスがわかりません。
そのため、プロセスに重きを置いた「PMBOK」「QC七つ道具」を一緒に使うことで、より一層効果を発揮することは間違いありません。
以下で、「PMBOK」「QC七つ道具」の活用方法について詳しく解説します。
PMBOKの活用方法
PMBOKとは、アメリカの非営利団体が作成したプロジェクトマネージメントのノウハウをまとめた知識を指します。
「Project Management Of Knowledge」の頭文字を取ったものであり、「10の知識エリア」「5つのプロセス」により構成されています。
活用方法は、まずQCDにより目標を設定。設定した目標を達成するため、どうすれば良いのかをPMBOKを使って考えます。
これにより、目標設定だけでなくそのプロセスにまで目を向けられるでしょう。
QC七つ道具の活用方法
ただ、PMBOKは万能ではないので、壁にぶつかることもあります。
そこで登場するのがQC七つ道具。
PMBOKでうまくいかなかった際に、「問題の発見」「問題の原因の把握」「問題が解決したかの確認法」を明確にできるフレームワークのことです。
「パレート図」「特性要因図」「グラフ(管理図を含む)」「チェックシート」「ヒストグラム」「散布図」「層別」の七つがあり、想定外のトラブルの原因特定に大いに役立ちます。
QCDフレームワークの派生語4つ

QCDフレームワークの派生語が以下のとおり4つあります。
- QCDS
- QCDSE
- QCDSM
- QCDF
それぞれの派生語について、以下で詳しく解説します。
「QCDS、QCDSE」とは?
Safety(安全)の「S」を加えることで「QCDS」となります。
また、そこにEnvironment(環境)の「E」を加えた「QCDSE」という言葉もあります。
建設業界においては、作業員の安全確保の必要性が高く、また環境にも配慮して施工をすることが重要です。
品質を保つには従業員の安全と健康があってこそなので、これらの要素も非常に大切になります。
QCDSやQCDSEについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
また、QCDSEについて、より詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
「QCDSM、QCDF」とは?
また、Safetyの「S」、Moral(やる気)の「M」を加えた「QCDSM」という言葉も。
従業員のやる気をいかに引き出すかにも着目をすることで、経営管理に使われることが多い言葉です。
さらに、Flexibility(柔軟性)の「F」を加えた「QCDF」という言葉もあります。
主に製造業やサービス業で使われますが、変化の激しい今の時代だからこそ、さまざまな変化に柔軟に対応する必要があります。
こうした社会情勢を鑑みて取り入れられた言葉が「QCDF」だといえるでしょう。
まとめ:QCDフレームワークで業務効率化を目指そう

今回は、QCDフレームワークについて解説しました。
QCDとは、費用や納期よりも「品質」に重きをおく考え方です。
QCDフレームワークをうまく使うことで、業務改善が図られ、従業員の質の向上にも繋がります。
また、QCDから派生したさまざまな言葉も出てきているので、一緒に理解をしておきましょう。
ぜひ、今回の内容を参考にして、社内の業務改善に取り組んでみてはいかがでしょうか?