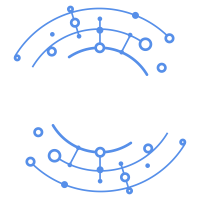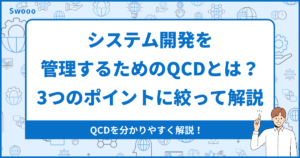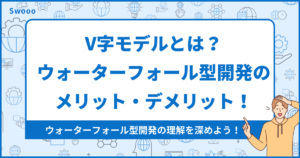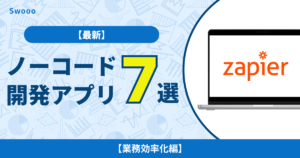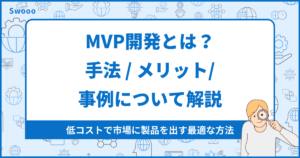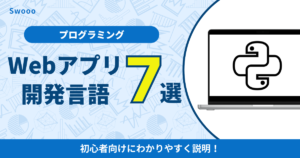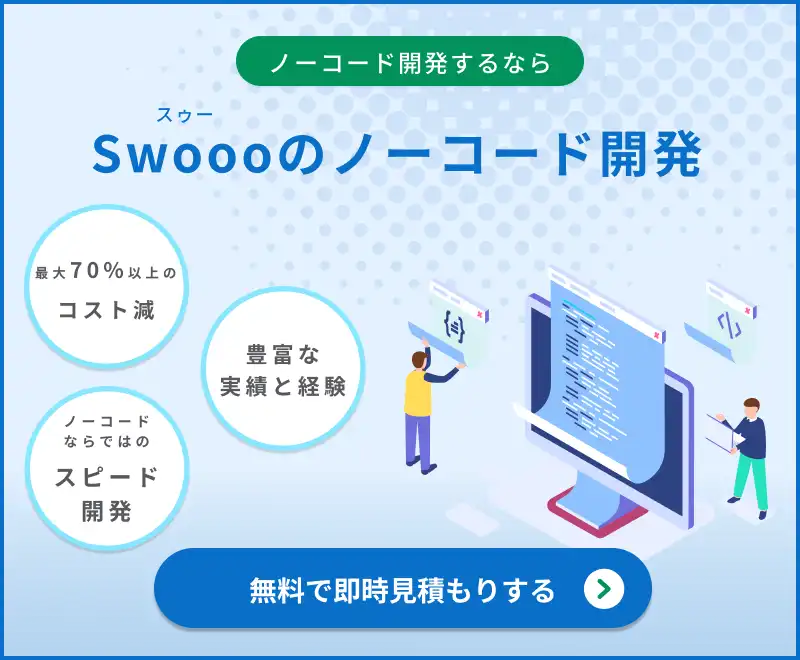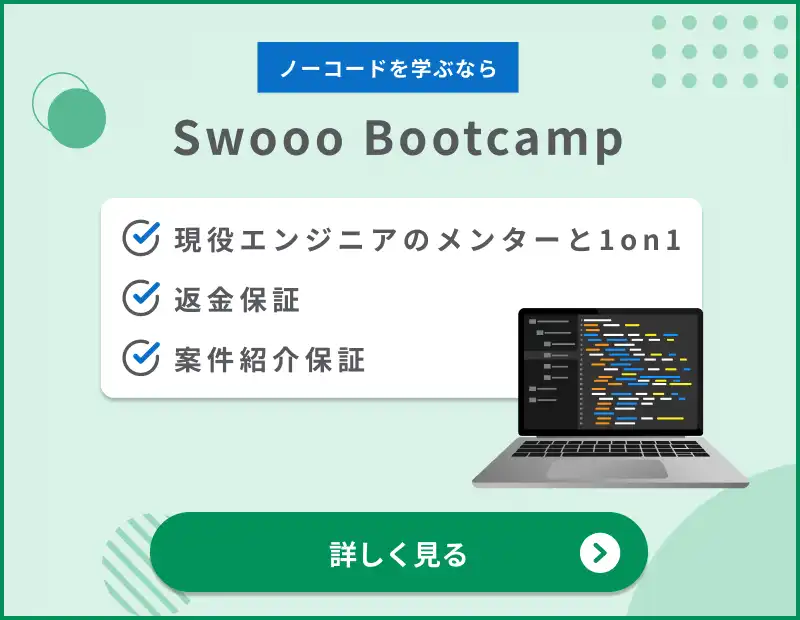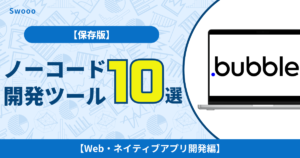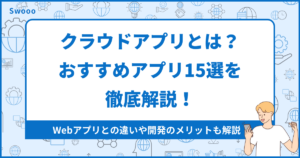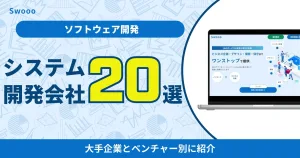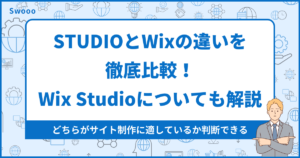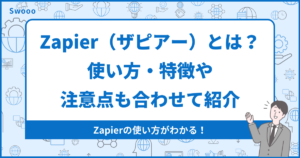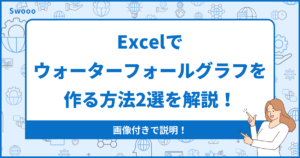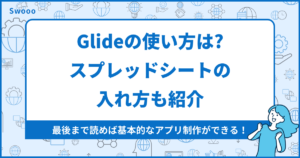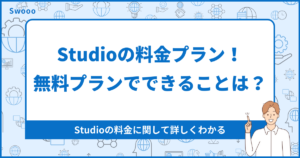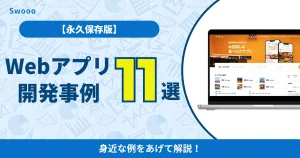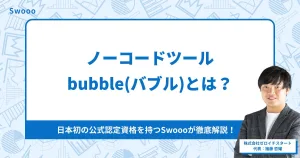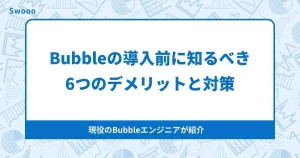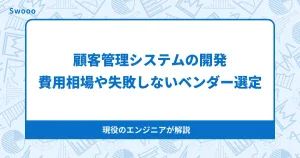【基礎】QCDとは?意味とポイントを徹底解説
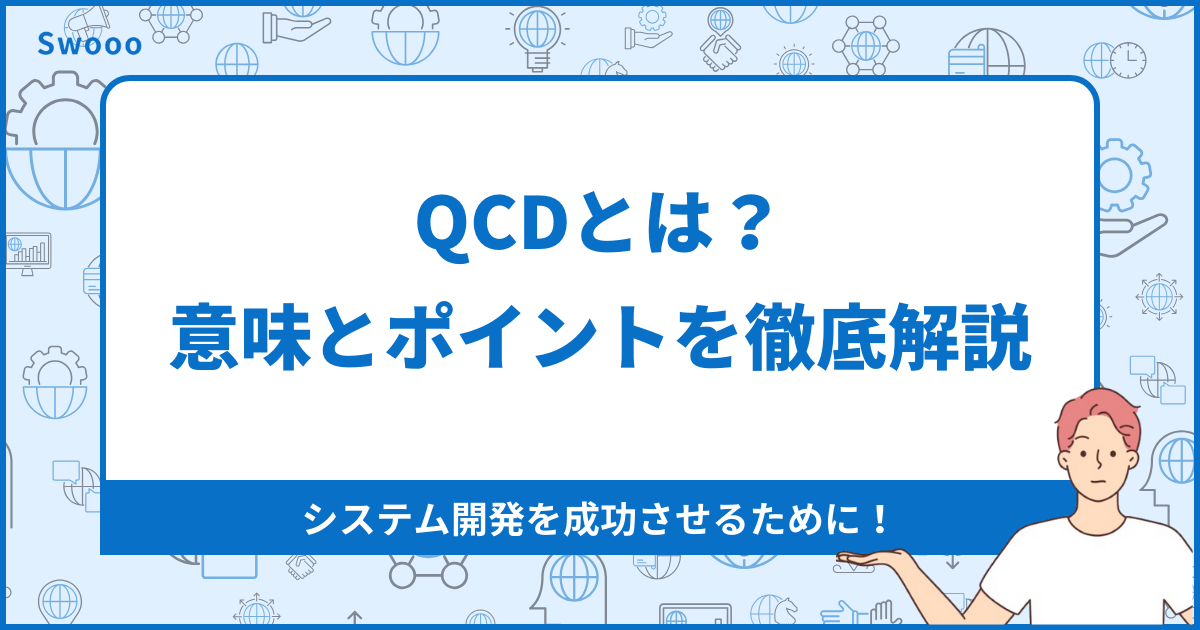
「システム開発をしているのだけど、よく聞くQCDって何?」
「QCDの概念を使えばプロジェクトがうまくいくって本当?」
システム開発をするうえでQCDという言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。
QCDとはプロジェクトを進めていくうえで欠かせない概念で、システム開発を成功させるためは、QCDの要素を取り入れることが不可欠です。
そんな重要なQCDについて意味や概念、実際に仕事において、どうやって活用していけばいいのかなどを解説しています。

この記事を読めばQCDの重要性と仕事への転用ができるようになります。それでは早速見ていきましょう。
目次
そもそもQCDとは?

QCDとは「Quality(品質)」「Cost(値段)」「Delivery(納期)」のことです。
それぞれの頭文字を取ってQCDと言います。
QCDは品質や値段、納期を徹底管理しなければならない製造業の分野において、もともとは使われていました。昨今では製造業に限らずIT業界やすべての業界で不可欠な概念で、ビジネス用語として目にする機会が増えています。
この3つの要素のうちの一つでも欠けたり問題があったりした場合は、プロジェクトやビジネスにおいて成功するのは難しくなると言われています。
▼こちらの記事も参考にしてください!
・QCDSとは?QC7つ道具、QCDSEについても解説
・システム開発を管理するためのQCDとは?3つのポイントに絞って解説
・【初心者必見】ITシステムにおけるQCDSEの意味を徹底解説!
QCDは相互に影響し合う関係
QCDの概念を知るうえで重要なのは、3つそれぞれの要素がバラバラではなく、相互に影響しあう関係だということを頭に入れておきましょう。
「Quality(品質)」「Cost(値段)」「Delivery(納期)」の3つの要素について、バランスよくすべて向上するように改善していくことが重要です。
例えば以下のような例が挙げられます。
- 商品開発において「品質」を重要視したところ、それだけ「費用」が増大してしまう
- 「費用」を抑えたところ、「品質」が下がってしまうことがある
- 「納期」を重視するためにスピードを上げて開発したが「品質」が下がってしまった
このように品質、値段、納期とQCDの3つの要素は、常に影響しあう関係になっており、すべての要素をいかにバランスよく向上させていくかが、QCDを活用するポイントとなっています。
Quality「品質」は最優先させる事項
QCDは並んでいる順番に重要度が高くなっています。
一番に重要視されるのは「Quality(品質)」で、その次に「Cost(値段)」、最後に「Delivery(納期)」の順番で続きます。
QCDで最も重要視されている「品質」ですが、顧客の満足度を最も高めてくれるのは、品質が良い製品だと言えます。
そのため、システム開発においてのQCDは、「顧客が望んだ製品ができたか」を最優先に置きましょう。

どんなに値段が安くても、納期がきっちりされたとしても、品質が劣っていたらすべて台無しです。
顧客が求めている品質を提供できなければ、顧客は離れていってしまうでしょう。
満足できる品質を開発できない場合は、他の業者との競争にも敗れてしまうというリスクも発生します。
このように品質は最重要なので、実際の開発においてはまず品質を高めることを最優先するようにしましょう。
Cost「費用」を抑えるためには
システム開発をする際にQCDにおいての「Cost(費用)」とは、「どうやって費用を適正価格に抑えて、プロジェクトを進めていくか」ということに留意します。
価格システム開発はもちろん、モノづくりの現場では必ず考慮されなければならない項目です。
システム開発の現場でコストが上昇する大きな原因となるのが、開発中に追加で発生する作業や修正の業務です。
価格を抑えるためには、開発に入る前にクライアントとの意思の疎通を徹底し、プロジェクトに対してのお互いの認識をしっかり確認しましょう。
途中で機能の追加や修正が入ると、どんどん価格が高騰していきます。

最悪の場合は、開発の途中で最初からやり直しという事例もありますので、それを避けることで価格の上昇を抑えることが可能になります。
Delivery「納期」
QCDにおいての「納期」は、「計画していたとおりに製品ができたか」を目指します。
QCDを念頭にシステム開発を進めていくと、納期の設定には頭を悩ませてしまう、という担当者も多いようです。
品質を重視するあまりに開発がどんどん延びてしまい、納期が遅れてしまうという事態におちいるからです。
エンジニアを増員しても、スキルが伴わないエンジニアの場合、そのフォローに時間とコストがかかりすぎて、思うようにプロジェクトが進まない場合もあります。
納期を短縮したい場合は、エンジニアを増やすよりも、スキルの高いエンジニアを始めからアサインすべきでしょう。

納期は早ければ早い方が良いというわけではなく、早すぎる納品は欠陥部分があるのではないか、とか工程を手抜きしたのでは?と疑われることもありえます。
納期はあくまでも予定したとおりに納品した方が良いでしょう。
Cost(値段)とDelivery(納期)は顧客の条件によって柔軟に対応する
QCDでは品質が最も優先されますが、値段と納期については顧客の要望や条件によって柔軟に対応しましょう。
何よりも品質確保を最優先し、コストと納期については顧客と綿密に打ち合わせをし、QCDが顧客にとって最も良い形で発揮されるように調整していくことが大切です。
QCDを達成するためのポイント
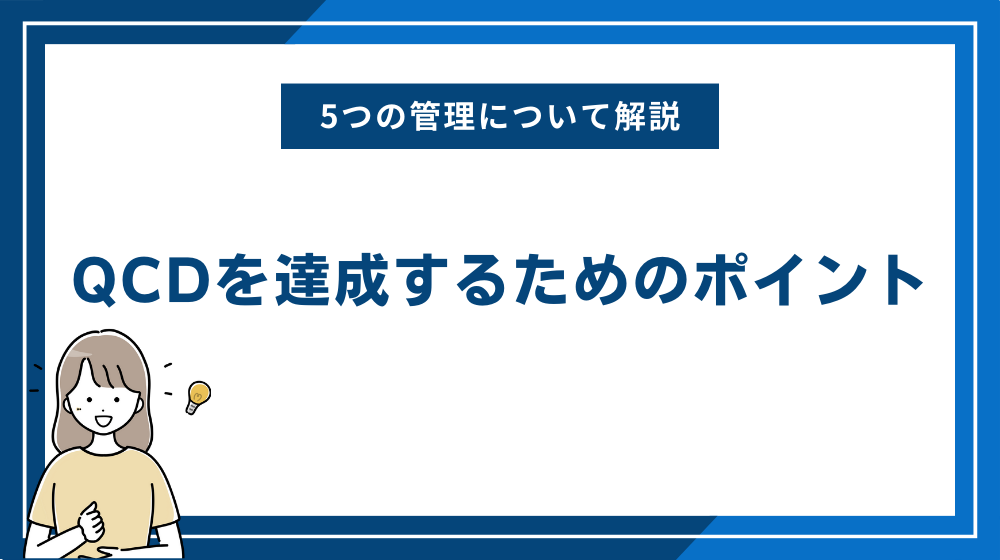
QCDについての意味や概念を分かったところで、実際にそれらを仕事で活かせることが大切です。
概念だけ知っていても業績を上げることはできません。QCDを達成するためには、作業や工程に合わせて作業や業務を管理することが必要になります。
また開発やプロジェクトの目標が曖昧だとQCDの手法が生かされなくなります。

ここからは、QCDを達成するために欠かせない5つの管理について解説していきます。
成果物のスコープを管理する
成果物スコープとは、プロジェクトを始める前に成果物を設定し、管理していく手法です。
開発において「何」を作るのかという点を明確にし、管理していきます。

例をあげると基本設計をする場合、最終目的である成果物は「設計書」という具合です。
このような形で管理をしていくと、成果物として実際に目に見える形でプロジェクトを確認しやすいため、プロジェクト全体の達成度合いが分かりやすい点があげられます。
また目標を明確に決めていくので、モチベーションを維持するのに役立ちます。
作業スコープを実施する
作業スコープは「プロジェクトスコープ」とも呼ばれています。
作業スコープは、プロジェクトで行うべき作業範囲を明確にして、作業を進めていく手法です。
この手法を取ると、どこまで開発すればよいのかが明確に示されるため、QCDにおいては値段を適切な価格でコントロールしやすい、また納期を予測しやすいといった利点があります。

例をあげると、基本設計をする場合、「データベースの設計の洗い出し」という作業を明確にしてからプロジェクトを進めていきます。
各工程では最初にどんな作業をするのかを明確にしておくことが大切です。この部分があいまいだと作業が進まなくなります。
チーム、コミュニケーション、リスクの管理をする
チーム管理は、チームを結成して管理していくやり方です。
この手法はメンバーのモチベーションを上げて現場の士気を高める効果があります。チーム結成においてメンバーのスキルや適性をしっかり把握することが求められます。
コミュニケーション管理とはプロジェクトに関する様々な情報を的確に把握し、共有、伝達をしていくことです。
コミュニケーション管理をすることで、メンバーのモチベーションやスキルアップ、業務の円滑化を図ることができます。
リスク管理も重要な項目の一つです。プロジェクトにおけるリスクを想定し、予防に努めることでQCDの向上につながることでしょう。
リスクが起きた場合にどのようなリスクが発生するのか、その規模や解決策をあらかじめシミレーションすることはプロジェクトの成功に欠かせません。
QCDは目的ではなく、手段である

QCDとはシステム開発やプロジェクトを成功させるための概念だと分かりました。
QCDは目的ではなく手段であり、QCDの概念である「高品質でコストがかからず納期に遅れない」ということを念頭に、開発を進めていくことが大切です。
システム開発に限らずすべてのモノづくりの現場で適用されるQCDを自社のプログラムに取り込むことで、より良い開発を目指すことができます。

QCDを使ってシステム開発を進めていきたいけれど、うまくいかない、実際の運用でつまずいているという方はぜひ弊社までご連絡ください。
弊社でもWeb開発・マーケティング支援を行っており、受託から開発後の管理まで一貫した安心感のある開発が可能です。
大手ITベンダー、大手Webディレクター2人体制でのプロジェクト管理を徹底しており、「当たり前品質」の高い価値提供ができます。
国内で費用を抑えてWeb開発やマーケティング支援をご希望の方はぜひお気軽にお問い合わせ下さい。